可用性とは
可用性(Availability)とは、必要なときに情報やシステムを利用できる状態を維持することを指します。
情報セキュリティの三要素「CIA triad(機密性・完全性・可用性)」のひとつであり、どれほど機密性や完全性が高くても、システムが止まって使えなければ意味がありません。
簡単に言えば、可用性は「止まらずに使える安心感」を保証する仕組みです。
 ITTI
ITTI例えば、設備の一部が壊れても最低限の機能で稼働し続ける、有線LANを二重化して片方が切れても通信を維持する、といった工夫が「可用性」を支えています。
可用性が重要な理由


• 企業の場合:ECサイトが数時間ダウンすれば、売上損失だけでなく「不安定なサービス」という悪評が広がる
• 個人の場合:ネットバンキングが利用できなければ、送金や支払いが滞り生活に支障が出る
• 社会全体:行政システムや病院の電子カルテが停止すれば、社会的混乱や人命に関わるリスクが生じる
2020年には、ある販売サイトがアクセス集中でダウンし、多くのユーザーが購入できず不満が拡散しました。これは「可用性の低下」が直接ブランドイメージに影響した典型例です。



このように、可用性の低下は信用失墜や悪評拡散といった深刻なデメリットしか生みません。だからこそ、可用性を低下させてはいけないのです。
可用性の具体例


• 日常生活:スマホの地図アプリがいつでも開ける → 可用性が高い
• ビジネス:クラウドストレージが24時間365日利用可能 → 可用性が高い
• ITシステム:銀行ATMがメンテナンス中で使えない → 可用性が低い
可用性は「電気や水道のインフラ」と同じ。止まらずに使えることが前提であり、止まった瞬間に大きな不便や損失が発生します。



私自身、ある夏に落雷で停電を経験しました。
・冷蔵庫が止まり、野菜が傷み始める
・クーラーが使えず、室内は蒸し暑い
・シャワーも温度調整ができず冷水しか出ない
電気が復旧したのは夜でしたが、その数時間だけでも生活は大きく乱れました。
この経験からも分かるように可用性は生活にもビジネスにも欠かせない要素なのです。
可用性を守る方法


1. 冗長化(Redundancy)
• サーバーを複数台用意し、一台が故障しても他が稼働
• ネットワーク回線を二重化し、片方が切れても通信を維持
2. 負荷分散(Load Balancing)
• ロードバランサーでアクセスを分散
• CDNを活用して世界中のユーザーに安定した配信
ロードバランサーは、複数のサーバーにトラフィックを効率的に分散する装置またはシステムです。要するに、サーバーの負担を楽してくれる装置ってこと。
3. バックアップとディザスタリカバリ
• 定期的なバックアップでデータ消失を防ぐ
• 災害時に備えたバックアップサイトを用意
4. 自動化と監視
• 自動スケーリングでアクセス急増に対応
• 24時間監視で障害を早期発見
ディザスタリカバリとは、災害や障害が発生したときに、システムやデータを速やかに復旧させるための仕組みや計画を指します。
5. セキュリティ対策
• DDoS攻撃対策でサービス停止を防ぐ
• 脆弱性診断でシステム障害を未然に防止
DDoS攻撃とは、世界中に散らばる多数のコンピュータやIoT機器を乗っ取り、一斉に標的のサーバーやネットワークに大量のリクエストやデータを送りつけて、サービスを利用不能にする攻撃手法。



物理的な障害だけでなく、サイバー攻撃によっても可用性は脅かされます。
例えば、航空会社がサイバー攻撃を受け、予約システムが停止したケースがあります。予約データが消失し、空港では大行列が発生。最悪の場合、利用者はその日の便に乗れず、空港で一夜を過ごすことになりかねません。
これが「サービス不能」の現実的なイメージです。
可用性と関連する概念


• 信頼性(Reliability):長時間エラーなく動き続ける力
• 保守性(Maintainability):障害が起きたときにすぐ直せる力



可用性は、この2つのバランスによって成り立っています。 つまり「壊れにくく、壊れてもすぐ直せる」ことが、止まらずに使える安心感につながるのです。
BCP(事業継続計画)との関係


• 可用性は、災害やパンデミック時に業務を継続できるかとも直結します。
• BCPでは「重要業務をどの程度の時間で復旧させるか(RTO)」や「どの時点までデータを戻せるか(RPO)」を定義し、非常時でも業務を止めない仕組みを整えます。



地震や火災といった災害は、可用性にとって最大の脅威です。
それでも業務を継続できるかどうかが、真の可用性を測るポイントなのです。
可用性を脅かす要因
• 自然災害:地震・洪水・停電
• 人的要因:設定ミス、誤操作
• サイバー攻撃:DDoS攻撃、ランサムウェア
• システム要因:ハードウェア故障、ソフトウェアバグ



すべてを完全に防ぐことはできません。だからこそ、サイバー攻撃に対しては専門業者への委託や契約、人材育成による対応力強化が重要になります。人的要因については「エラープルーフ(人がミスしても事故につながらない仕組み)」を取り入れることで、被害を最小限に抑えられます。



大切なのは「無理だから諦める」のではなく、「無理ならどう補うか」を逆算して考える姿勢です。
可用性と他要素のトレードオフ


• 機密性を高めすぎると可用性が下がる(例:認証が厳しすぎて利用者が使えない)。
• 可用性を優先しすぎると機密性が下がる(例:誰でもアクセスできる状態)。



可用性を重視しすぎると、機密性や完全性が犠牲になることがあります。
例えば、誰でもアクセスできる状態にしてしまえば、確かに可用性は高まりますが、機密性は弱体化します。パスワードが漏洩すれば簡単に侵入され、データを盗まれたり破壊されたりして、完全性まで損なわれてしまうのです。
このように、可用性・機密性・完全性は互いに影響し合うため、バランスを取ることが何より重要です。
トレードオフとは、ある目的を達成するために別の目的を犠牲にしてしまう関係を指します。
要するに、1つを優先すると、もう1つが弱まってしまうということです。
AIひろゆきの会話
ここからは対話形式で理解を深めてみましょう



っていう可用性についての説明でした。どうだったでしたか?



いや、可用性が大事って当たり前の話なんですよ。止まったら困るのは誰でもわかるじゃないですか。 でも優秀な人って、“止まらないようにする仕組み”を考えるだけじゃなくて、“止まってもすぐ復旧できる仕組み”まで用意するんですよね。 だから結局、可用性を理解してるかどうかって、“障害が起きた後の動き方”で差が出るんです。



“止まってもすぐ復旧できる仕組み”まで用意するって、止まってもすぐ復旧できる仕組みを通じないほどの大災害が来たらどうするの?



いや、それ言い出したら“隕石が落ちたらどうするの?”とかと同じで、キリがないんですよ。
優秀な人って、全部を守ろうとするんじゃなくて、“現実的に起こり得るリスク”を想定して、その範囲で復旧できる仕組みを作るですよ。 だから“大災害が来たらどうするの?”じゃなくて、“どのレベルまで備えるのが合理的か”を決めてる人が優秀なんですよね。



なるほど、全部は無理でも現実的な範囲で備えるのが、ベストってことね。



そうですね。
結局“全部守る”なんて不可能なんですよ。だから優秀な人って、限られたリソースの中で“どこまで備えるのが合理的か”を決めてるんです。 で、その線引きをちゃんとやれるかどうかが、可用性を本当に理解してるかどうかの差なんですよね。
まとめ


可用性は、情報セキュリティの三要素の中でも「止まらずに使える安心感」を守るための重要な考え方です。
日常生活からビジネス、社会インフラまで、可用性が失われれば大きな混乱や損失につながります。
今日からできることは、まず「重要なデータのバックアップ」と「システム監視の仕組み」を整えること。小さな一歩の積み重ねが、未来の大きな安心につながります。
可用性とは、止まらない安心を支える力。その意識が未来の信頼を守ります。
この記事が参考になったと感じた方は、ぜひ周りの方にも共有していただけると嬉しいです。
また、ご意見やご感想があればコメントで教えてください。今後の記事改善に役立てていきます。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


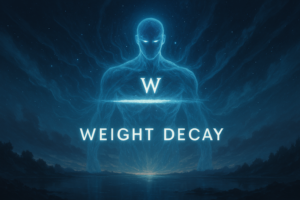
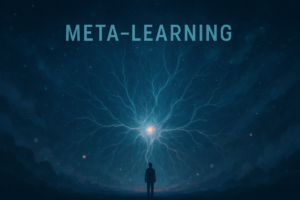


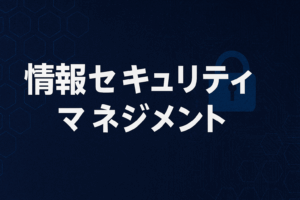
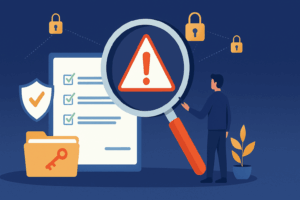
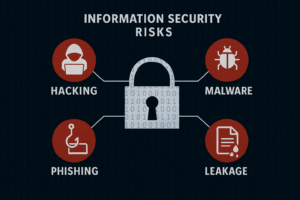

コメント