機密性とは?
機密性(Confidentiality)とは、許可された人だけが情報にアクセスできる状態を保つことを指します。情報セキュリティの三要素「CIA triad(機密性・完全性・可用性)」のひとつであり、特に個人情報や企業の機密データを守る上で欠かせません。情報セキュリティマネジメント試験でも頻出の基本概念です。
機密性の重要性

• 企業の場合:顧客データや設計図が漏洩すれば、信用失墜や損害賠償につながる
• 個人の場合:住所やクレジットカード情報が流出すれば、なりすまし被害や不正利用のリスクがある
 ITTI
ITTI機密性の欠如は経済的損失に直結します。例えばクレジットカード番号が流出すれば金銭被害だけでなく、企業は信頼を失い、巨額の賠償責任を負う可能性があります
機密性が損なわれた実際の事件


• 大手企業の顧客情報流出事件
• 医療機関でのカルテ漏洩
• クラウドサービスの設定ミスによる情報公開



最大の原因は「人為的なミス」と「サイバー攻撃」です。
“面倒だから”と対策を省略した瞬間に、機密性は崩れます。
機密性の具体例


• 日常生活:LINEやメールの内容は、本人以外が勝手に見られないようパスワードや暗号化で守られている
• ビジネス:病院では患者のカルテを閲覧できるのは担当医や看護師に限定されている
• ITシステム:クラウドサービスでは、アクセス権限を設定して「営業部だけが顧客リストを見られる」ように制御している
機密性は「鍵付きの米蔵」のようなもの。誰でも入れる納屋に米を置いておけば盗まれるのと同じで、大事な情報は“鍵”をかけて守る必要があります。
機密性を守る方法


技術的対策
• データの暗号化
• アクセス制御(ID・パスワード、二要素認証)
• 通信のSSL/TLS化
人的対策
• 社員教育(情報の取り扱いルールを徹底)
• 情報持ち出し制限(USBや外部サービスの利用制御)
物理的対策
• 入退室管理(ICカードや生体認証)
• 監視カメラや施錠によるオフィスセキュリティ



技術的対策のレベルが高ければ高いほど、不正アクセスや盗聴による突破を防ぎやすくなります。
人的対策のレベルが高ければ高いほど、誤操作や内部不正を防ぎ、組織全体の信頼性が高まります。
物理的対策のレベルが高ければ高いほど、盗難や不正侵入による情報流出を防ぎやすくなります。
脅威の具体例


• 内部不正(社員や委託先による持ち出し)
• フィッシングやマルウェアによる情報窃取
• 盗聴(Wi-Fi盗聴やパケットキャプチャ)



例えば、重要な情報を保存したUSBを外部に持ち出すことは大きなリスクです。
また、フィッシングは「お得なキャンペーン」や「偽の緊急性」といった甘い誘い文句で利用者をだまし、情報を入力させる典型的な手口です。
さらに、公共Wi-Fiを利用すると通信が盗聴され、どのサイトを開いたかや入力した情報が第三者に知られてしまう危険があります。
機密性と他の要素との関係


• 機密性が破られると → 完全性(改ざんリスク)も同時に損なわれる
• 可用性を優先しすぎると → 機密性が犠牲になる(例:誰でもアクセスできる状態)



機密性が損なわれると、完全性と可用性にも被害が及びます。
例えば、機密性が破られればデータが改ざんされ、正確性(完全性)が失われます。
さらに、攻撃や不正利用によってシステムが停止すれば、利用者が業務や生活に支障をきたし、可用性も損なわれます。
最新トピックとの接続
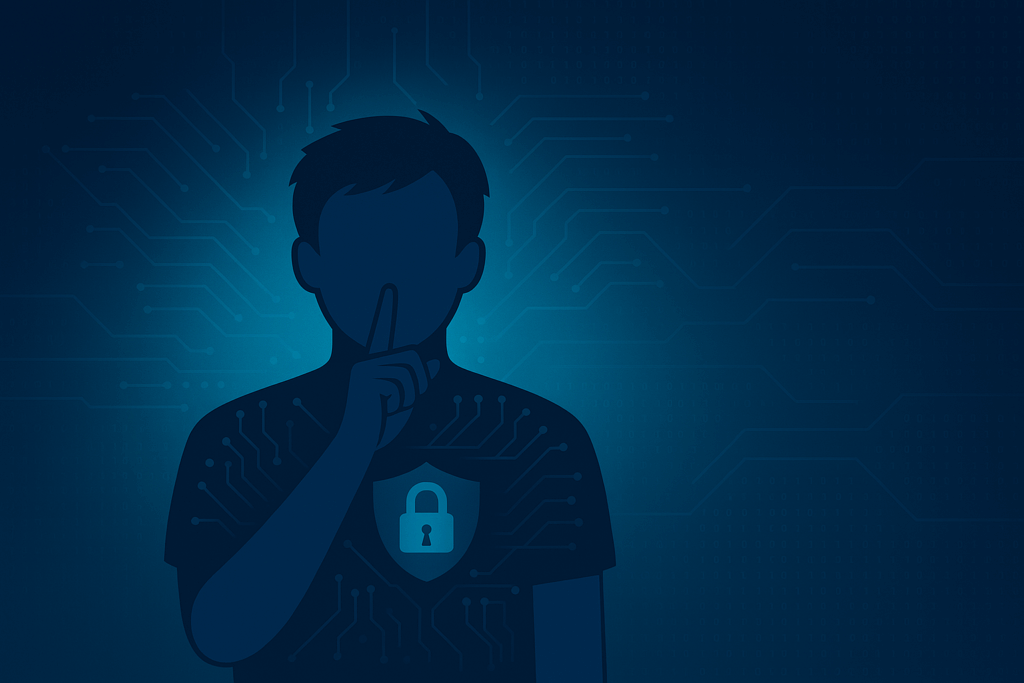
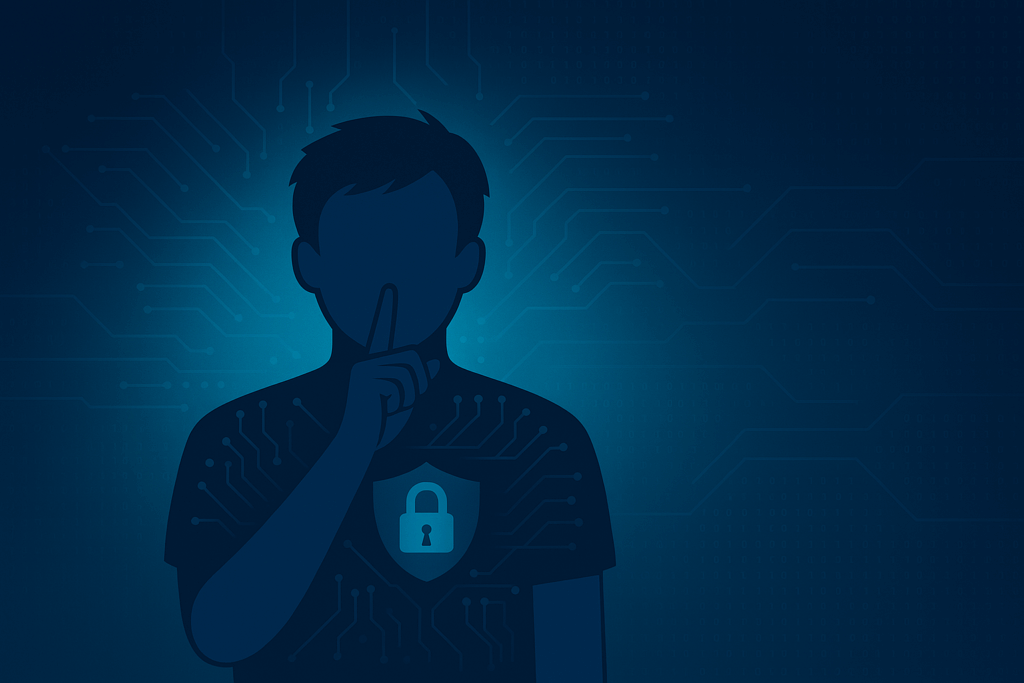
ゼロトラストセキュリティ(「誰も信用しない」を前提にアクセス制御)



ゼロトラストセキュリティは「内部も外部も信用しない」を前提にした戦略で、仮に内部にスパイが潜んでいても不正アクセスを防げる仕組みです。
クラウド時代の機密性確保(SaaSの設定ミス、シャドーIT問題)



クラウド時代では、SaaSの設定ミスやシャドーITが大きなリスクになります。許可されていないクラウドに業務データを保存すれば、設定不備や無許可利用によって流出し、顧客への賠償やブランド価値の低下といった損害を企業が負う可能性があります。
生成AI利用時の情報漏洩リスク(入力したデータが外部に渡る可能性)



生成AIの利用も注意が必要です。例えば、社外秘の情報をそのまま入力してしまうと、サービスによっては入力データが学習に利用される場合があり、外部に漏れるリスクも否定できません。
実際に大手メーカーでソースコードが入力され、情報流出リスクが問題となった事例も報道されています。こうした背景から、利用ルールの整備は欠かせません。
AIひろゆきの会話
ここからは対話形式で理解を深めてみましょう



っていう機密性についての説明でした。どうだったでしたか?



いや、機密性が大事っていうのは分かるんですけど、結局“人間が面倒くさいからやらない”ってところが一番のリスクなんですよね。
暗号化とかアクセス制御とか言っても、設定するのは人間ですし。
だから“技術的な仕組み”よりも“人間がサボらない仕組み”を作らないと、結局は同じことの繰り返しになるんじゃないですか?



人間がサボらない仕組みってどんな仕組みですか?



いや、サボらない仕組みなんて基本的に存在しないんですよ。
人間って必ずサボるんで。
だから“仕組みを作る”んじゃなくて、“サボっても被害が出ないようにする”のが現実的なんですよね。
二要素認証とか自動バックアップとか、本人がサボっても勝手に守られる仕組みを入れるしかないんじゃないですか?



サボっても被害が出ないようにするって、結局は改ざんや不正を繰り返すだけになりませんか?
それなら何もしない人でも被害は出ないんですか?



いや、何もしない人がいても別に被害は出ないんですよ。
だって“何もしない人”はシステムを壊さないですから。
問題なのは“ちょっと触って間違える人”とか“勝手に便利なサービスを使う人”なんですよね。
だから結局、“サボる人”より“余計なことをする人”をどう止めるか。
それが機密性を守る上で一番大事なんじゃないですか?



なるほど、つまり機密性を確保するには“人に任せない仕組み”が必要なんですね。
二要素認証で解除しないと入れない、自動バックアップで勝手に保存される、社内カードがないと会社に入れない。
こうした仕組みで強制力を持たせることで、より堅牢な機密性を実現できると思いますしね。



結局そこなんですよ。
人間に任せると必ずサボるし、余計なこともする。
だからこそ“人に任せない仕組み”を作ることが、機密性を守る唯一の現実的な方法なんです。
セキュリティって技術の話に見えて、実は「人間の弱さを前提に設計できるかどうか」っていう話なんですよね。
だからこそ、機密性は“人間の弱さを前提にした仕組み”によってしか守れないんですよ。
まとめ


機密性は情報セキュリティの基盤です。
機密性を守る最大のポイントは、“人間の弱さを前提にした仕組み”です。
今日からできることは、まず「誰がどの情報にアクセスできるべきか」を整理し、不要な権限を削除することです。 小さな一歩が、大きなリスク低減につながります。
どうでしたか?今回は機密性について詳しく説明してみました。
この記事が参考になったと感じた方は、ぜひ周りの方にも共有していただけると嬉しいです。
また、ご意見やご感想があればコメントで教えてください。今後の記事改善に役立てていきます。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


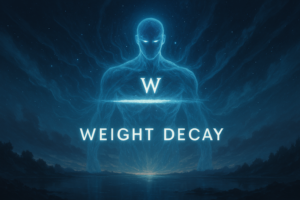
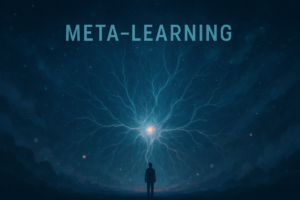


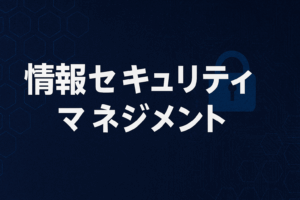
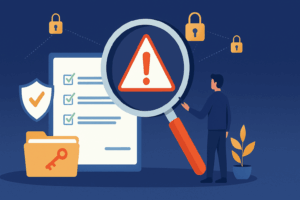
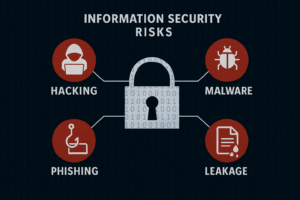

コメント