責任追跡性とは
責任追跡性(Accountability)とは、情報システムにおける操作や行為を記録し、後から「誰が、いつ、何をしたか」を明確にできる性質を指します。
情報セキュリティの三要素(機密性・完全性・可用性)に加え、ISO/IEC 27001などの国際規格では「真正性」「否認防止」「信頼性」と並んで重要な要素とされています。
簡単に言えば、責任追跡性は「証拠を残す仕組み」。不正や事故が起きたときに、原因や責任を明らかにできることがポイントです。
 ITTI
ITTI例えば、オフィスで鍵を返却するときに「返却簿に自分の名前と時間を書く」ことも責任追跡性の一例です。
また、監視カメラで入退室の様子を記録することも同じ仕組みです。
ITシステムではこれが「ログ」として残り、後から誰がどんな操作をしたかを確認できるようになっています。
責任追跡性が重要な理由


• 企業の場合:顧客データが削除されたとき、誰が操作したのか追跡できなければ原因究明も再発防止もできない
• 個人の場合:自分のアカウントから不正送金が行われたとき、ログがなければ「自分がやっていない」と証明できない
• 社会全体:行政システムや選挙システムで操作履歴が残らなければ、不正が疑われても検証できず、制度への信頼が崩壊する。



責任追跡性が欠けていると、不祥事は草のように伸びていきます。
最初は小さな芽でも、放置すればやがて大きな問題となり、発覚したときには手遅れです。
その成長を止めるのが「記録」です。
記録はまるで干ばつのように、不正の芽を枯らしてしまう。
証拠が残る環境があれば、不祥事は根を張る前に抑え込めるのです。
責任追跡性の具体例


• 日常生活:ネットショッピングで「注文履歴」が残る → 誰がいつ購入したか追跡できる
• ビジネス:社内システムで「誰がどのファイルを開いたか」をログに記録 → 内部不正の抑止につながる
• ITシステム:銀行のオンラインバンキングで「ログイン履歴」「送金履歴」が残る → 不正アクセスの証拠になる
責任追跡性は「防犯カメラ」と同じ。普段は意識しなくても、トラブルが起きたときに「証拠」として役立ちます。



履歴はまるで「草を除去するスプレー」のようなものです。
不祥事という草は、放っておけばどんどん伸びてしまいますが、履歴というスプレーをかければ芽のうちに枯らすことができます。
しかも、履歴は自動的に残る仕組みであることが理想です。
「記録が残る」と意識するだけで、不正をしようとする心も自然と萎んでいきます。
だからこそ、責任追跡性は組織にとって最強の抑止力になるのです。
責任追跡性を確保する方法


ログ管理
• システムやアプリケーションの操作履歴を記録
• ログの改ざん防止(WORMストレージやハッシュ値で保護)
アクセス制御
• ユーザーごとにIDを発行し、共有アカウントを禁止
• 誰が操作したかを明確にする
認証の強化
• パスワードだけでなく二要素認証を導入
• なりすましを防ぎ、正しい利用者を特定
監査とモニタリング
• 定期的にログを監査し、不審な操作を検知
• SIEM(セキュリティ情報イベント管理)ツールでリアルタイム監視



様々な方法がありますが、「どれが一番強いのか?」と聞かれれば、答えはシンプルです。
結局、ログ管理・アクセス制御・認証・監査のすべてを組み合わせてこそ、本当の責任追跡性が実現します。もちろん、これ以外にも補助的な方法はありますが、基本の4つを揃えることが最優先です。
部分的な対策では抜け穴が残ります。しかし全体をそろえれば「言い逃れできない環境」が完成し、顧客や社会からの信頼を確実に得ることができるのです。
責任追跡性を脅かすリスク


• 共有アカウントの利用:誰が操作したか特定できない
• ログの未収集・未保存:証拠が残らない
• ログの改ざん:不正を隠蔽される
• 監査不足:記録があっても活用されない



草を除去するスプレーを買うように、責任追跡性を確保する仕組みを外部委託するのも有効です。
専門性を持つ委託先に任せれば、記録の収集や監査を確実に行ってくれるため、不祥事の芽を早めに枯らすことができます。
つまり、委託は「草剃りサービス」を導入するようなもの。だからこそ、外部委託は組織にとって信頼性を高める有効な選択肢なのです。
AIひろゆきの会話
ここからは対話形式で理解を深めてみましょう



っていう責任追跡性についての説明でした。どうだったでしたか?



いや、全部やれば信頼を得られるって言いますけど、
実際には「やってます」ってアピールしてるだけで、
中身が形骸化してる組織も多いんですよね。
監査ログがあっても誰も見てないとか、
アクセス制御してても管理者アカウントがザルとか。
結局、「仕組みを入れること」よりも
「それをちゃんと運用する人がいるかどうか」の方が大事なんですよ。



国からの認定を得られるとか、国際からの認定を得らればよくないっすか?



いや、国とか国際機関の認定を取れば安心って思う人多いですけど、
実際には「認定を取るための書類作り」とか「審査対応」が目的化してる組織も多いんですよね。
で、現場の運用は全然追いついてないとか。
ISOの認定持ってても、共有アカウント使ってる会社とか普通にありますからね。
結局、認定って「外向けの看板」にはなるけど、
中身が伴ってなければ意味ないんですよ。



じゃあ、中身を見える化にして、みんなが安心して使える方法は?



いや、中身を見える化すれば安心って言いますけど、
結局「見える化」って言葉だけで満足してる組織が多いんですよね。
ダッシュボード作ってグラフ並べても、
誰も見てないとか、見ても理解できないとか。
で、「見える化してます」ってアピールだけして、
実際には現場の人が不安なまま使ってるケースもあるんですよ。
本当に安心につなげたいなら、
見える化より「それをどう使うか」とか「誰が責任を持つか」を決める方が大事なんですよね。



どうすればいいんだよおおおおおおおお!



いや、どうすればいいんだよって言いますけど、
別に難しいことじゃなくて「やるべきことをちゃんとやる」だけなんですよね。
ログを残すとか、共有アカウントやめるとか、
二要素認証入れるとか、基本的なことをサボらない。
結局、不正が起きる組織って「面倒だからやらない」って理由がほとんどなんですよ。
だから「どうすればいいか?」って聞く時点で、
もうやらない言い訳を探してるだけなんじゃないですかね。



なるほど、だったら、不正もなく真面目にやっていけばいいんだよね。直感的には、不正を起こさせないには報連相が大事かなと思いますね。



まぁ、真面目にやって報連相を大事にするっていうのは、普通に正しいと思うんですよ。
結局、不正を防ぐ仕組みって「技術」と「人の習慣」の両方が揃ってこそ意味があるんで、報連相がちゃんと回ってる組織は、それだけで強いんですよね。
だから、仕組みに頼りすぎず、人の関係性も大事にする。結局それが、一番シンプルで効果的なんですよね。
まとめ


責任追跡性は、情報セキュリティにおいて「証拠を残し、責任を明確にする」ための重要な要素です。
今日からできることは、まず 「共有アカウントをやめ、個人ごとのIDでログを残す」 こと。これだけでも責任追跡性は大きく向上します。
今回は責任追跡性について詳しく説明しました。
ログや証拠を残すことは否認防止にもつながりますし、記録の仕組みだけでなく、人間関係の在り方も重要です。お互いに柔軟性を持ち、尊敬し合い、報連相を徹底することで、不正の芽を早めに摘み取ることができます。
結局、責任追跡性は“信頼を失わないための最低条件”。
これを整えているかどうかで、組織の未来は大きく変わるのです。
この記事が参考になったと感じた方は、ぜひ周りの方にも共有していただけると嬉しいです。
また、ご意見やご感想があればコメントで教えてください。今後の記事改善に役立てていきます。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


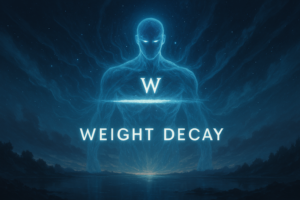
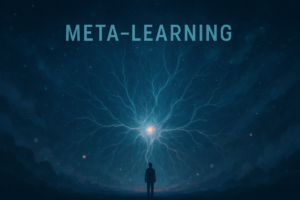


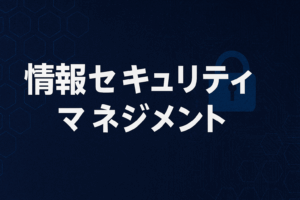
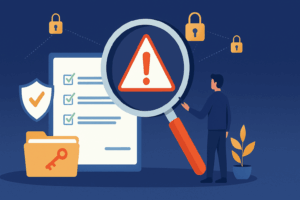
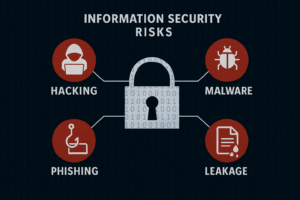

コメント