否認防止とは何か
情報セキュリティの基本要素といえば「機密性・完全性・可用性(CIA)」が有名ですが、近年はこれに「真正性・責任追跡性・否認防止・信頼性」を加えた 7要素 が重視されています。
その中の「否認防止(Non-repudiation)」とは、ある操作や取引を「自分はやっていない」と後から言い逃れできないようにする仕組みのことです。
 ITTI
ITTI『自分はやってない』って言うだけじゃ通用しないように、それが通じないことを示せる仕組みが必要です。
なぜ否認防止が必要なのか


• 電子契約で「署名していない」と言われたら契約が無効になる
• メール送信後に「送っていない」と否定されたら業務が混乱する
• 社内システムで「操作していない」と言われたら責任追及ができない



こうしたトラブルを防ぐためには、否認防止が必要です。だから、「やったことを証明できる仕組み」を作らなければなりません。
否認防止を実現する技術


電子署名・デジタル署名
公開鍵暗号方式を利用し、本人しか持たない秘密鍵で署名することで「確かにその人が行った」と証明できる。
タイムスタンプ
データが「いつ存在していたか」を証明。契約や研究データの改ざん防止に有効。
ログ管理・監査証跡
誰が・いつ・どの操作をしたかを記録。改ざんできない形で保存することが重要。
二要素認証(2FA)
「パスワード+スマホ認証」などを組み合わせることで本人性を強化。
ブロックチェーン
改ざんが困難な分散型台帳を利用し、取引や記録の正当性を担保。



証拠が残る仕組みを作れば、後から『やってない』は通用しない。これが否認防止の本質です。
実務での具体例


電子契約
A社とB社がクラウド契約サービスを利用。後からB社担当者が「署名していない」と否認しても、電子署名とタイムスタンプで本人の操作が証明される。
社内システム
農業法人で販売データを入力した社員が「自分じゃない」と否定しても、ログにユーザーIDと操作履歴が残っていれば責任を明確化できる。



大事なのは透明性です。透明性を高めるには記録が欠かせません。
記録があれば後から確認できますし、嘘をついていないかも検証できます。 積極的にログを残しておけば、後悔することはなくなるでしょう。
否認防止を強化するための運用ポイント


• 定期的にログを監査し、改ざんや不正がないか確認する
• 電子署名や二要素認証を導入し、本人性を確実に担保する
• 社員教育を行い、「否認防止は信頼を守るための仕組み」と理解してもらう



監査役は最強の剣。教育は最強の盾。両方そろってこそ、否認防止は本当に機能する。
強化のポイント
• 技術(署名・ログ・暗号化)+ 運用(監査・教育・権限管理)の両輪で進める
• 「証拠が残る仕組み」を徹底する
• 「言い逃れできない環境」を作ることで、組織の信頼性を高める。



『自分の行動はちゃんと記録されている』という意識があるだけで、人は不正に手を出しにくくなるんだよね。結局、証拠が残る環境が最大の抑止力になる。
AIひろゆきの会話
ここからは対話形式で理解を深めてみましょう



っていう否認防止についての説明でした。どうだったでしたか?



『自分の行動はちゃんと記録されている』という意識があるだけ。
いや、否認防止って“やったことを証明できる仕組み”なんで、優秀な人とかまともな会社は最初から導入してるんですよ。逆にこれを入れてない組織って、“不正してもバレない環境を放置してます”って言ってるようなもんなんですよね。だから結局、優秀な人はこういう仕組みをちゃんと使うし、使わないところには優秀な人は集まらないんですよ。



最高情報セキュリティ責任者と監査役だけで居ればよくないっすか?



いや、それって“責任者と監査役がいれば全部解決する”って思ってる時点で、仕組みを理解してないんですよ。結局、現場の社員が日々どう動くかとか、システムがどう記録を残すかっていう“仕組み全体”がないと意味ないんですよね。
最高責任者と監査役だけ置いても、証拠が残らなければ『やってない』って言い放題になるんで。だから優秀な会社は“人+仕組み”の両方をちゃんと整えてるんですよ。



経営者が最高情報セキュリティ責任者を監視すればよくないっすか?



あなたの感想ですよね笑
それって“経営者が見てれば全部解決する”って思ってる時点で、現実をわかってないんですよ。経営者って会社全体の意思決定や資金繰りで手一杯なんで、セキュリティの細かい監視なんて物理的にできないんですよね。
結局、仕組みとしてログを残すとか、権限を分けるとか、監査を定期的にやるとか、そういう“システム全体”がないと意味がないんですよ。経営者が一人で監視しても、証拠が残らなければ『やってない』って言い放題になるんで。
だから優秀な会社は“トップの目”に頼るんじゃなくて、“仕組み+人”で抑止力を作ってるんですよ。



そうですね、責任者や監査役に任せるだけじゃなくて、監視カメラや社員教育も必要ですよね。『あなたの行動は記録されている』という意識があるだけで、不正の抑止力になりますし。



そうそう。結局“人+仕組み+意識づけ”の三つがそろわないと、否認防止は機能しないんですよ。だから優秀な会社はそこをちゃんとやってるんですよね。
まとめ


「情報セキュリティマネジメントにおける否認防止は、単なる技術的な仕組みではなく、組織や取引先との信頼を守るための約束事です。
『やっていない』と言われても証明できる仕組みを整えることは、ビジネスの継続性や信用力を高める大切な投資といえます。
まずは自社のログ管理や電子署名の導入状況を点検し、否認防止の仕組みが十分かどうか確認してみましょう。
どうでしたか?今回は否認防止について詳しく説明してみました。
以前は「機密性・完全性・可用性(CIA)」だけで十分だと思っていましたが、否認防止が欠けると“嘘が増える”というリスクがあることが分かりました。やはり信頼を守るには欠かせない要素ですね。
この記事が参考になったと感じた方は、ぜひ周りの方にも共有していただけると嬉しいです。
また、ご意見やご感想があればコメントで教えてください。今後の記事改善に役立てていきます。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


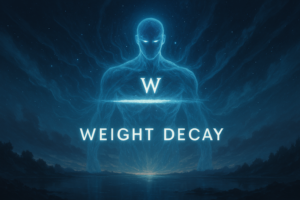
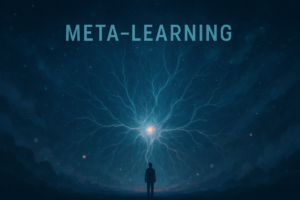


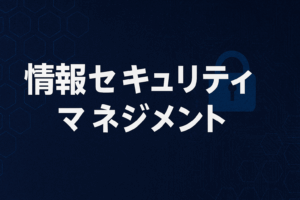
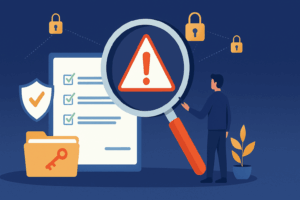
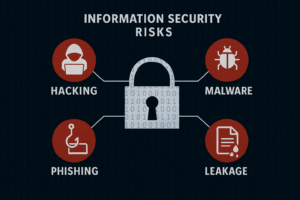

コメント