信頼性とは?
情報セキュリティの世界では「CIA triad(機密性・完全性・可用性)」が有名ですが、実はそれを支える要素のひとつに 信頼性(Reliability) があります。
信頼性とは、システムや仕組みが期待通りに動き続けることを意味します。
例えば
◦ 毎日バックアップを取る設定にしている → 実際に毎日成功しているか?
◦ ログイン認証がある → 障害で止まらず、常に正しく動いているか?
◦ データを保存した → 後から壊れずに取り出せるか?
 ITTI
ITTIつまり「動くはずのものが、ちゃんと動く」こと。
人間でいえば「約束を守る」「嘘をつかない」存在に近いのです。
なぜ信頼性が大事なのか?


初心者の方は「セキュリティ=ハッカー対策」と思いがちですが、実際には人為的なミスやシステムの不具合が大きなリスクになります。
• バックアップが取れていなかった → ランサムウェアに感染しても復旧できない
• 認証サーバーが落ちた → 社員が誰もシステムに入れない
• ログが欠損していた → 不正が起きても追跡できない
これらは「攻撃」ではなく「信頼性不足」による事故です。



そして、もし障害や不具合が起きたときに改善せず言い訳ばかりしていれば、顧客や取引先からの信頼は一気に失われます。
信頼を失う → 契約を打ち切られる → 収益源を失う → やがて倒産リスクに直面する。
だからこそ、信頼性は“生き残るための条件”なのです。
信頼性が損なわれた例


• クラウドの設定ミス:誰でもアクセスできる状態にしてしまい、顧客情報が流出
• USBの紛失:バックアップはあったが暗号化されておらず、情報が漏洩
• システム障害:認証サーバーが落ちて、社員が業務できなくなるこれらは「信頼性が低い」状態の典型例です
信頼性を高める方法


技術的な工夫
• バックアップと復元テスト:保存するだけでなく、実際に戻せるか確認する
• 二重化(冗長化):サーバーやネットワークを複数用意して、片方が壊れても動くようにする
• ログ管理:誰が何をしたかを記録し、改ざんされないように保護する
人的な工夫
• 教育・ルール作り:パスワードを使い回さない、怪しいメールを開かない
• 権限の見直し:退職者や異動者のアカウントを放置しない
運用の工夫
• 定期点検:システムが正しく動いているかをチェックする
• 演習:障害やサイバー攻撃を想定して復旧訓練を行う



信頼性を保つには、人間がルールを守り、仕組みを正しく運用することが欠かせません。
しかし現実には「点検や確認をサボる」「お得なキャンペーンに釣られて怪しいメールを開く」といった人間の行動が、信頼性を崩す最大の原因になります。
信頼性と他の要素との関係


• 機密性:信頼性がなければアクセス制御も崩れる
• 完全性:信頼性がなければデータが壊れたり改ざんされる
• 可用性:信頼性がなければ「使いたいときに使えない」



信頼性は、機密性・完全性・可用性を下から支える“土台”のような存在です。
初心者が今日からできること


• 自分のパソコンやスマホの バックアップを定期的に確認する
• パスワードを強化し、二要素認証を有効にする
• 不要なアカウントや権限を削除する
• 公共Wi-Fiでは VPNを使う。



一人で学ぶだけでなく、研修や勉強会に参加するのも効果的です。 最新の事例や他人の失敗談から学べるので、実践的な知識が身につきます。
AIひろゆきの会話
ここからは対話形式で理解を深めてみましょう



っていう信頼性についての説明でした。どうだったでしたか?



いや、信頼性が大事っていうのは分かるんですけど、結局“人間がちゃんとやる”って前提がそもそも無理なんですよね。
人間って必ずサボるし、確認もしないし、怪しいメールも開くんですよ。
だから「人間が頑張れば信頼性は保てます」っていうのは、現実的じゃないんです。
むしろ“人間がサボっても壊れない仕組み”を作ることが、本当の信頼性なんじゃないですか?



人間がサボっても信頼性を壊さない仕組みって具体的な内容は?



いや、人間がサボるのは当たり前なんで、そもそも「ちゃんとやってね」ってお願いする時点で無理なんですよ。
だから“サボっても壊れない仕組み”っていうのは、例えばこういうやつです。
・バックアップは自動で取るし、定期的に復元テストもスケジュールで回す
・二要素認証を必須にして、本人がパスワードを雑に扱っても突破できないようにする
・権限は自動で棚卸しされて、退職者や異動者のアカウントは勝手に無効化される
・監視ログは外部に転送されて、誰も消せないようにする
要するに“人間に任せない”ってことなんですよ。
人間がサボっても、仕組みが勝手に守ってくれる。
それが本当の意味での信頼性なんじゃないですか?



でも、こうやってシステムばかりに任せていると、もし突然システムが壊れて、修理に1年かかるとしたら? その間はどうするの? 結局、人間にお願いするしかないの?



もしシステムが壊れて、長期間直らないって状況になったらどうするの?
それって結局、“代替手段を用意してるかどうか”の話なんですよ。
例えば、
・クラウドが止まったら、ローカルに最低限のデータを持っておく
・自動化が使えないなら、紙やエクセルで一時的に業務を回す手順を決めておく
・復旧までの間は、人間がやる作業を“最小限”に絞って、優先度の高い業務だけ続ける
要は「全部止まったら終わり」じゃなくて、“もしも”のときにどう縮小運転するかを決めておく。
それがBCP(事業継続計画)ってやつで、信頼性を守る最後の砦なんですよね。



確かに、事業継続計画を作っておけば、システムは人間がサボっても仕組みが支えてくれるので、信頼性を保てるんですね。だからこそBCPが欠かせないんですね。



まあ、そうなんですよね。
人間に期待するより、仕組みに任せた方が安定する。で、その仕組みが壊れたときにどう動くかを決めておくのが事業継続計画なわけで。
結局、“人間はサボるもの”って前提に立った方が、信頼性って本当に長持ちするんですよ。
まとめ


- 信頼性とは「システムが期待通りに動き続けること」
- 重要性:攻撃だけでなく、ミスや障害からも情報を守るために必須
- 方法:バックアップ、冗長化、教育、演習などで強化できる
- 初心者でもできること:バックアップ確認(復旧できるかを保証)、パスワード強化(二要素認証で不正ログインを防ぐ)、不要権限削除(攻撃者の入り口を減らす)
信頼性は、情報セキュリティマネジメントの基盤です。
「人間の弱さ」や「システムの不具合」を前提に、壊れても守れる仕組みを作ることが、安心につながります。
今回の記事が少しでも参考になったら、ぜひ身近な人にも教えてあげてください。
また、ご意見やご感想をコメントでいただけると、今後の記事改善に役立ちます。
情報セキュリティの基盤となる“信頼性”について解説。なぜ重要なのか、具体的な強化方法、初心者でも今日からできる対策まで分かりやすくまとめました
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


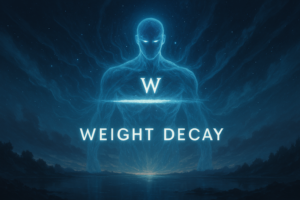
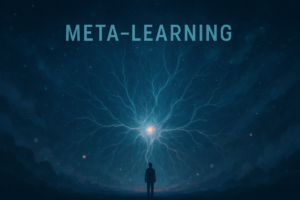


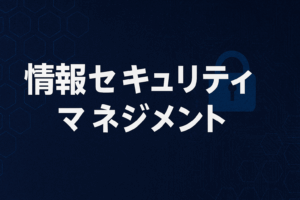
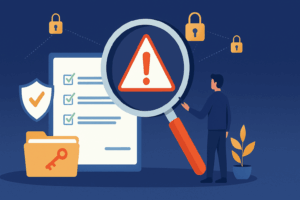
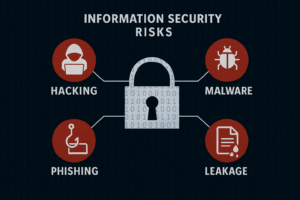

コメント