脅威とは
情報セキュリティにおける脅威(threat)とは、システムやデータに損害を与える可能性のある要因や事象を指します。
- リスク:脅威が実際に損害を与える可能性
- 脆弱性:脅威が成立しやすくなる弱点
つまり、脅威 × 脆弱性 = リスク という関係で理解すると整理しやすいです。
 ITTI
ITTI脅威は、サイバー攻撃や不正アクセス、マルウェア感染、さらには自然災害のように、システムやデータに損害を与える可能性のある要因を指します。
一方で脆弱性は、セキュリティホールや弱いパスワード、鍵の紛失といった、脅威が成立しやすくなる弱点のことです。
そしてリスクは、こうした脅威と脆弱性が結びついた結果、実際に情報漏洩や業務停止といった被害が発生する可能性を意味します。
脅威の分類


脅威は大きく以下の3つに分けられます。
- 人為的脅威
- 意図的:不正アクセス、マルウェア感染、内部不正
- 偶発的:誤送信、設定ミス、機器紛失
- 環境的脅威
- 地震、火災、落雷、停電、クラウド障害など
- 社会的脅威
- サプライチェーン攻撃、ビジネスメール詐欺、犯罪のビジネス化



つまり、人のミスも脅威であり、自然災害も脅威であり、サイバー攻撃も脅威です。組織の信頼性を損ない、事業にダメージを与える要因はすべて脅威といえます。
代表的な脅威の例


IPA「情報セキュリティ10大脅威」などを参考にすると、以下が代表的です。
- ランサムウェア:データを暗号化し、身代金を要求する攻撃
- 標的型攻撃メール:特定組織を狙った偽装メールによる侵入
- 内部不正:従業員による情報持ち出しや改ざん
- ゼロデイ攻撃:修正プログラム公開前の脆弱性を突く攻撃
- ビジネスメール詐欺(BEC):経営者や取引先を装い送金をだまし取る
- サプライチェーン攻撃:取引先や委託先を経由して侵入
- テレワーク環境の脆弱性悪用:家庭用Wi-FiやWeb会議システムを狙う



「情報セキュリティ10大脅威」とは、その年に社会的影響が大きかったと考えられる脅威を専門家が選定したリストです。
つまり、毎年の動向を反映した「今まさに注意すべき代表的な脅威」を示しており、企業や個人が優先的に対策を検討すべき指標となります。
脅威がもたらす影響


- 社会的信用の失墜:顧客離れ、ブランド価値低下
- 法的リスク:個人情報保護法やGDPR違反による罰則
- 経済的損失:システム復旧費用、損害賠償、株価下落
- 事業継続への打撃:業務停止、長期的な売上減少



脅威を適切に防げず、実際に被害を受けた企業は「任せられない」と判断され、顧客や取引先からの信頼を失います。その結果、ブランド価値の低下から契約解消、最悪の場合は倒産に至るケースもあります。
一方で、脅威に対して迅速かつ的確に対応できる企業は「この会社は信頼できる」と評価され、契約や売上の増加につながります。
つまり、脅威への対応力は企業の存続と成長を左右する決定的な要素なのです。
脅威への対策


脅威対策は「技術」「人」「組織」の3方向から進めるのが基本です。
- 技術的対策:ファイアウォール、多要素認証、暗号化、バックアップ
- 人的対策:従業員教育、フィッシング訓練、内部統制
- 組織的対策:CSIRT設置、インシデント対応計画、フレームワーク活用(ISMS、NIST CSF)



高度な技術を導入し、人材育成を徹底し、さらに国際的なフレームワークを活用することで、強固で持続可能なセキュリティ体制を備えた組織を築くことができます。
最新動向


最新の脅威動向としては、以下の3つが注目されています。
- 犯罪のビジネス化:攻撃ツールやサービスがダークウェブなどで売買され、専門知識がなくても誰でも攻撃を仕掛けられる環境が整いつつあります。
- AIを悪用した攻撃:生成AIを利用したフィッシング文書やディープフェイク詐欺が現実化しており、今後はAIを活用した高度なサーバー攻撃が登場する可能性も指摘されています。
- クラウド依存リスク:クラウドに過度に依存すると、クラウド側で障害や設定ミスが発生した際に、利用企業の情報が一斉に流出するリスクがあります。



これらはいずれも、従来のセキュリティ対策だけでは防ぎきれない新たな課題であり、企業は最新の動向を踏まえた継続的な対策強化が求められています。
AIひろゆきの会話
ここからは対話形式で理解を深めてみましょう



以上が脅威の説明でした。どう思いますか?



いや、それって「用語を並べただけの教科書」なんですよ。優秀な人って、知識を知って満足するんじゃなくて、それをどうやって実務に落とし込むかを考えるんですよね。
結局、リスクアセスメントを回して、CSIRTを立ち上げたり、ISMSやNIST CSFみたいなフレームワークを活用して、仕組みとして回せる体制を作る。ここまでやって初めて“脅威に強い会社”って言えるんですよ。
逆に「脅威は理解してます」で止まってる会社ほど、実際に被害を受けやすいんですよね。



要は、この記事を読んで“へぇ〜”で終わらせずに、すぐ行動しろってことですよね。



そうですね、優秀な人って、知識を仕入れたらすぐに小さくても実行に移すんですよね。
結局、セキュリティって「知ってるかどうか」じゃなくて「仕組みとして回せるかどうか」で差がつくんですよ。
だから、記事を読んで終わりにする会社と、読んだ瞬間に教育や仕組みづくりに着手する会社、ここで将来の信頼性に大きな差が出るんですよね。



脅威を摘み出すためには、技術的対策・人的対策・組織的対策を学び、社内で実践し、改善策として提案を経営層に提案することが有効です。
さらに、自らCISO(最高情報セキュリティ責任者)の役割を担う意識を持ち、主体的に取り組むことで、組織全体のセキュリティ水準を高めることができます。


まとめ


脅威とは、サイバー攻撃や内部不正、自然災害など、組織の信頼性や事業継続を脅かす要因を指します。脆弱性と結びつくことでリスクとなり、情報漏洩や業務停止といった深刻な被害を引き起こします。
企業が生き残るためには、技術・人・組織の3方向から脅威対策を進め、最新動向を踏まえて継続的に改善することが不可欠です。脅威は「起きないもの」ではなく「必ず起きるもの」として備える。
──これが、信頼を守り、成長を続ける企業の条件です。
この記事が参考になったと感じた方は、ぜひ周りの方にも共有してください。ご意見やご感想があればコメントで教えてください。今後の改善に役立てます。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


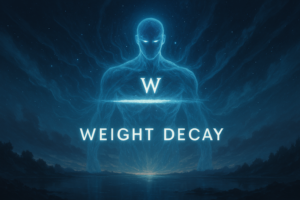
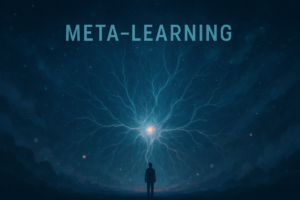


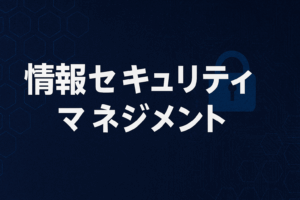
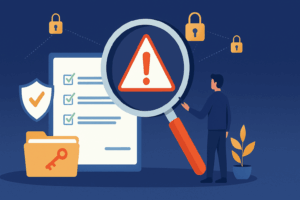
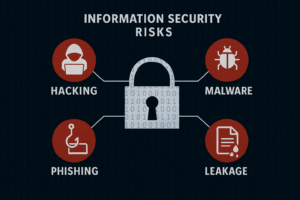

コメント