はじめに:なぜ今「データ利活用」が注目されているのか
 穹詠/情報セキュリティマネジメント主任
穹詠/情報セキュリティマネジメント主任「うちの会社もDXを進めないと」「データを活用しないと生き残れない」という言葉を、最近よく耳にしませんか?ニュースやビジネス誌でも「データドリブン経営」「AI活用」といったキーワードが毎日のように登場しています。
しかし、「データ利活用って具体的に何をすること?」「業務分析って難しそう…」と感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、企業経営における業務分析とデータ利活用について、専門知識がなくても理解できるように、2026年の最新トレンドを交えながら解説していきます。
第1章:そもそも「業務分析」「データ利活用」とは何か


業務分析とは
業務分析とは、会社の中で行われている仕事(業務)を細かく調べて、「どこに問題があるか」「どうすればもっと効率よくできるか」を見つけ出す作業のことです。
たとえば、あなたが毎日行っている仕事を思い浮かべてください。その仕事には「時間がかかりすぎている部分」「ミスが起きやすい部分」「そもそも必要なのか疑問な部分」があるかもしれません。こうした点を明らかにするのが業務分析です。
具体的には以下のような観点で分析します。
- 作業時間:その仕事にどれくらいの時間がかかっているか
- コスト:人件費や材料費などがいくらかかっているか
- 品質:ミスや不良品がどれくらい発生しているか
- フロー:仕事の流れに無駄や重複がないか
データ利活用とは
データ利活用とは、会社が持っているさまざまな情報(データ)を集めて分析し、経営判断や業務改善に役立てることです。
私たちの周りには、実はたくさんのデータがあふれています。
- 売上データ:いつ、何が、いくら売れたか
- 顧客データ:どんなお客様が、どのくらいの頻度で購入しているか
- 在庫データ:商品がどれくらい残っているか
- 従業員データ:誰が、どの仕事に、どれくらいの時間を使っているか
- 機械データ:工場の設備がどのように稼働しているか
これらのデータを「ただ保存しておく」のではなく、「分析して意味のある情報に変える」ことが、データ利活用の本質です。
第2章:2026年、データ利活用はどう変わったか
AIエージェントの登場 ― 「指示待ちAI」から「自律型AI」へ
2026年に入り、最も大きな変化は「AIエージェント」の普及です。
これまでのAI(人工知能)は、「質問に答える」「文章を作る」といった受け身の作業が中心でした。つまり、人間が指示を出さないと動かない「指示待ちAI」だったのです。
しかし2026年のAIエージェントは違います。「目標を与えれば、自分で計画を立て、必要な情報を集め、実際に作業を行う」という自律的な動きができるようになりました。
たとえば、「出張の手配をして」と指示するだけで、AIエージェントが以下を自動で行います。
- スケジュールを確認
- 最適な交通手段を検索
- ホテルを予約
- 経費精算書を作成
- 上司に承認依頼を送信
IBMの調査によると、2026年末までに企業の70%がこうしたAIエージェントの導入を予定しています。これまで人間が何時間もかけていた作業が、数分で完了する時代が始まっています。
データの「一元管理」が当たり前に
2026年のもう一つの大きなトレンドは、「データファブリック」や「データメッシュ」と呼ばれる新しいデータ管理の考え方が広まったことです。
難しい言葉ですが、簡単に言えば「会社中のデータを、誰でも簡単に見つけて使える状態にする」ということです。
これまで多くの企業では、営業部門、製造部門、経理部門など、部署ごとにバラバラにデータを管理していました。そのため、「全社の売上を知りたい」というだけでも、各部門に問い合わせて、データを集めて、フォーマットを揃えて…という膨大な手間がかかっていました。
2026年には、こうしたデータが一つの「データ基盤」に集約され、必要なデータを検索するだけで瞬時に取り出せる環境が整いつつあります。まるでインターネットで検索するように、社内のあらゆるデータにアクセスできるイメージです。
セキュリティとガバナンスの強化
データ活用が進む一方で、2026年8月にはEUの「AI法」が完全施行されました。AIの不適切な利用には最大3,500万ユーロ(約50億円以上)、または世界売上高の7%という巨額の罰金が科される可能性があります。
日本企業も無関係ではありません。グローバルに事業を展開する企業はもちろん、AIサービスを利用するすべての企業が、データの適切な管理とAIの責任ある利用を求められています。
具体的には以下のような対応が必要です。
- データの出所管理:どこから取得したデータなのかを記録する
- アクセス権限の設定:誰がどのデータを見られるかを厳格に管理する
- AIの判断の説明責任:AIがなぜその結論を出したのかを説明できるようにする
第3章:具体的にどんな業務でデータ活用が進んでいるのか
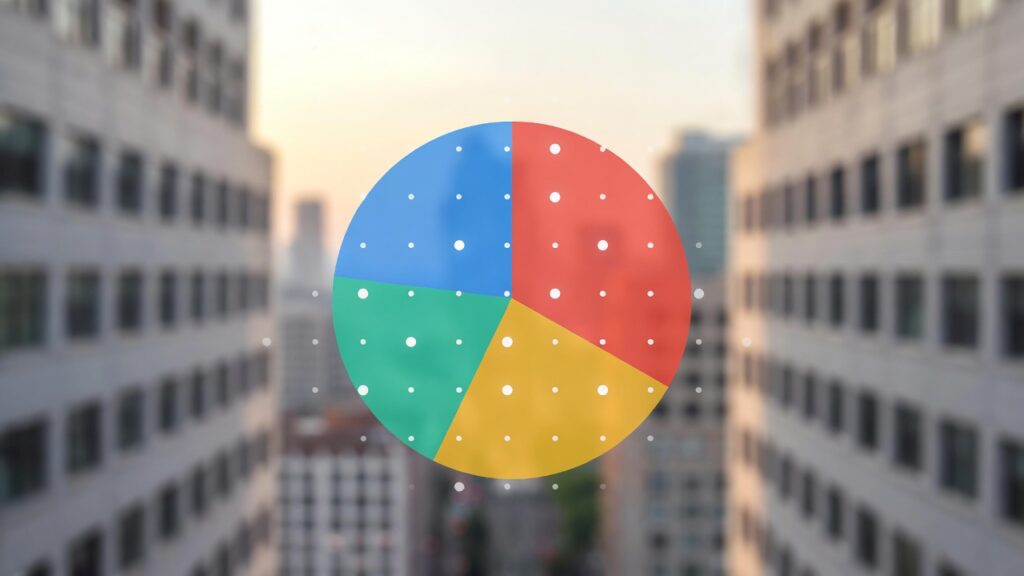
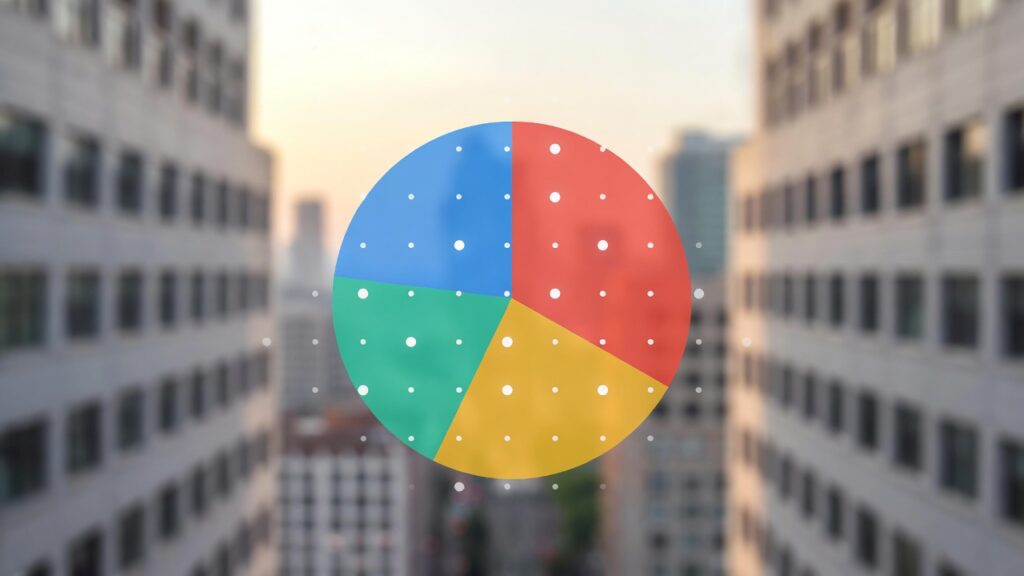
経理・財務部門
経理部門では、請求書処理、経費精算、財務レポート作成といった定型業務の自動化が急速に進んでいます。
たとえば、紙の請求書をスキャンするだけで、AI-OCR(文字認識技術)が金額、日付、取引先名などを自動で読み取り、会計システムに登録してくれます。人間は確認するだけで済むようになりました。
NECが2026年1月に提供を開始した「cotomi Act」というサービスでは、経費精算、受発注業務、審査業務などを、曖昧な指示にも対応しながらAIが自動処理します。これまで「人の判断が必要」と思われていた業務も、AIが担えるようになってきています。
営業・マーケティング部門
営業部門では、顧客データの分析による「需要予測」が活用されています。
過去の購入履歴、問い合わせ内容、Webサイトの閲覧履歴などを分析することで、「この顧客は来月に追加注文をする可能性が高い」「この顧客は解約リスクがある」といった予測ができるようになりました。
これにより、営業担当者は「可能性の高い顧客」に集中してアプローチでき、効率的に成果を上げられます。また、解約しそうな顧客には事前にフォローを入れることで、顧客維持率を向上させることができます。
製造・物流部門
製造業では、工場の機械から取得するIoTデータ(センサーデータ)の活用が進んでいます。
機械の温度、振動、稼働時間などのデータをリアルタイムで監視し、AIが「この設備は3日後に故障する可能性がある」と予測します。これを「予知保全」と呼びます。故障してから修理するのではなく、故障する前にメンテナンスすることで、ダウンタイム(停止時間)を最小限に抑えられます。
物流分野では、需要予測AIと在庫管理AIと配送最適化AIが連携し、「どの商品を、どれだけ、どの倉庫に置くか」「どのルートで配送するか」を自動で最適化するシステムが実用化されています。
人事・総務部門
人事部門では、採用業務や研修管理にAIが活用されています。
履歴書の自動スクリーニング、面接日程の自動調整、適性検査の分析などが自動化され、採用担当者は「人を見極める」という本質的な業務に集中できるようになっています。
また、IBMの調査によると、経営層は2026年末までに従業員の56%でリスキリング(新しいスキルの習得)が必要になると予測しています。AIと人間の役割分担を明確にし、AIでは対応できない業務に人材を集中させる動きが加速しています。
第4章:データ活用の効果 ― 実際にどれくらい成果が出ているのか


大手企業の成功事例
2025年から2026年にかけて、多くの企業がAI・データ活用で具体的な成果を上げています。
パナソニックコネクトは、生成AIの全社導入により、年間44.8万時間の業務時間削減を達成しました。これは約200人分の年間労働時間に相当します。
ソニーグループは、生成AIの活用で毎月5万時間の削減を実現。年換算で60万時間、約300人分の業務効率化につながっています。
JALでは、全グループ従業員が利用する生成AIアプリケーションを導入し、グランドスタッフの90%以上が「効率が向上した」と実感しています。
日経の調査では、AIを仕事で使う人の74%が作業効率の向上を実感しているという結果が出ています。特に情報収集や資料作成の時間削減に効果があるようです。
中小企業でも効果は出る
「大企業だからできるんでしょ?」と思うかもしれませんが、中小企業でもデータ活用の効果は十分に得られます。
たとえば、Excelで管理している売上データを分析するだけでも、「どの商品が、どの時期に、どのくらい売れるか」というパターンが見えてきます。専門的な知識がなくても、テンプレートを使えば簡単なトレンド分析は可能です。
重要なのは、「ビッグデータ」という言葉に惑わされず、まずは自社が持っているデータから活用を始めることです。売上データ、顧客リスト、在庫情報など、身近なデータでも十分な効果を発揮します。
第5章:データ活用を始めるための3ステップ
ステップ1:現状を把握する
まずは、自社の業務がどうなっているかを正確に把握することから始めます。
具体的には、以下の点を洗い出します。
- どんな業務があるか:日々の仕事を書き出してみる
- どれくらい時間がかかっているか:各業務にかかる時間を計測する
- どんなデータが発生しているか:業務の中で作成・使用している情報を整理する
- どこに課題があるか:時間がかかりすぎ、ミスが多い、手作業が多い業務を特定する
この段階で大切なのは、「現場の声を聞くこと」です。実際に業務を行っている人が、一番課題を理解しています。
ステップ2:小さく始める
いきなり全社でAIシステムを導入するのは危険です。まずは「一つの業務」「一つの部門」で試験的に始めましょう。
たとえば、以下のような「始めやすい業務」から取り組むのがおすすめです。
- 頻度が高い業務:毎日行っている業務は、効果を実感しやすい
- 定型的な業務:ルールが明確な業務は、自動化しやすい
- データが揃っている業務:すでにデータが蓄積されている業務は、分析しやすい
失敗しても影響が小さい範囲で実験し、うまくいったら範囲を広げていく「スモールスタート」のアプローチが成功の鍵です。
ステップ3:人材を育てる
データ活用を定着させるには、「使いこなせる人」を増やすことが不可欠です。
IBMの調査によると、AI活用を歓迎する従業員は、抵抗する層の2〜3倍に達しています。また、61%の従業員が「仕事がより戦略的になった」と感じており、63%が「AIとの協働に前向き」と回答しています。
AIは「仕事を奪う」ものではなく、「単調作業から解放し、より付加価値の高い仕事に集中させてくれる」ものだと理解してもらうことが重要です。
そのためには、社内研修やワークショップを通じて、実際にAIツールを触ってもらう機会を設けましょう。「使ってみたら意外と簡単だった」という体験が、抵抗感を払拭してくれます。
第6章:よくある失敗パターンとその対策


失敗1:期待しすぎ
「AIを入れれば全部自動化される」と期待していたが、実際には人間のチェックや判断が必要な場面が多く、がっかりした…というパターンです。
対策:AIは万能ではありません。「どこまでをAIに任せ、どこからは人間が判断するか」を事前に明確にしておきましょう。現時点では、AIは「補助ツール」として位置づけ、最終判断は人間が行う体制が安全です。
失敗2:現場の抵抗
経営層の判断でAIツールを導入したが、現場が「使い方が分からない」「今のやり方で十分」と抵抗し、結局使われなかった…というパターンです。
対策:導入前から現場を巻き込み、「何に困っているか」「どんな機能があれば助かるか」をヒアリングしましょう。現場が「自分たちのためのツールだ」と感じれば、抵抗感は大きく減ります。
失敗3:データの質が悪い
AIを導入したが、元になるデータが不正確・不完全で、まともな分析ができなかった…というパターンです。
対策:「ゴミを入れればゴミが出る(Garbage In, Garbage Out)」という言葉があります。AIの精度はデータの質に依存します。ツール導入の前に、まずデータの整備(重複の削除、フォーマットの統一、欠損値の補完など)に取り組みましょう。
第7章:2026年以降の展望 ― これからどうなるのか
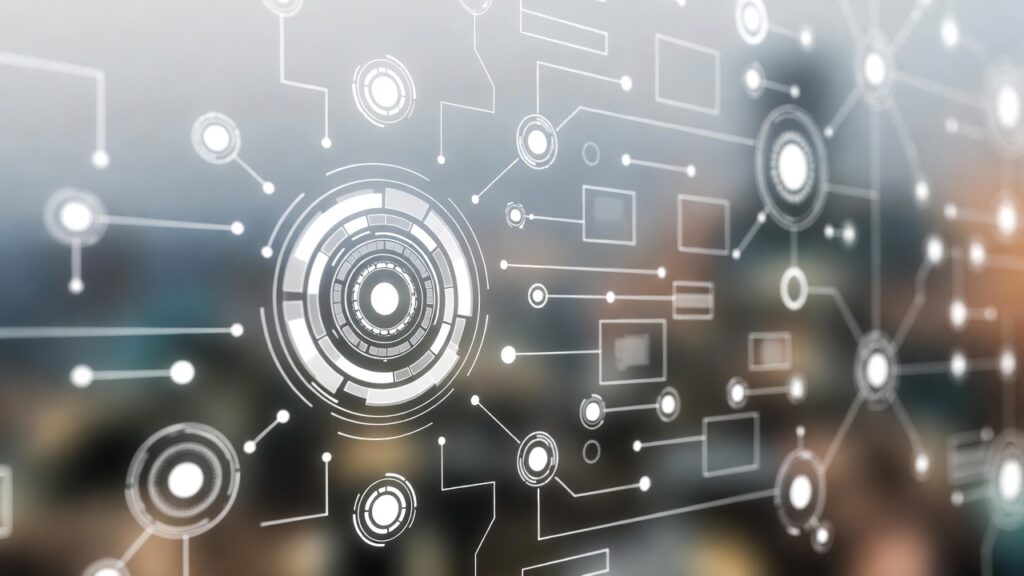
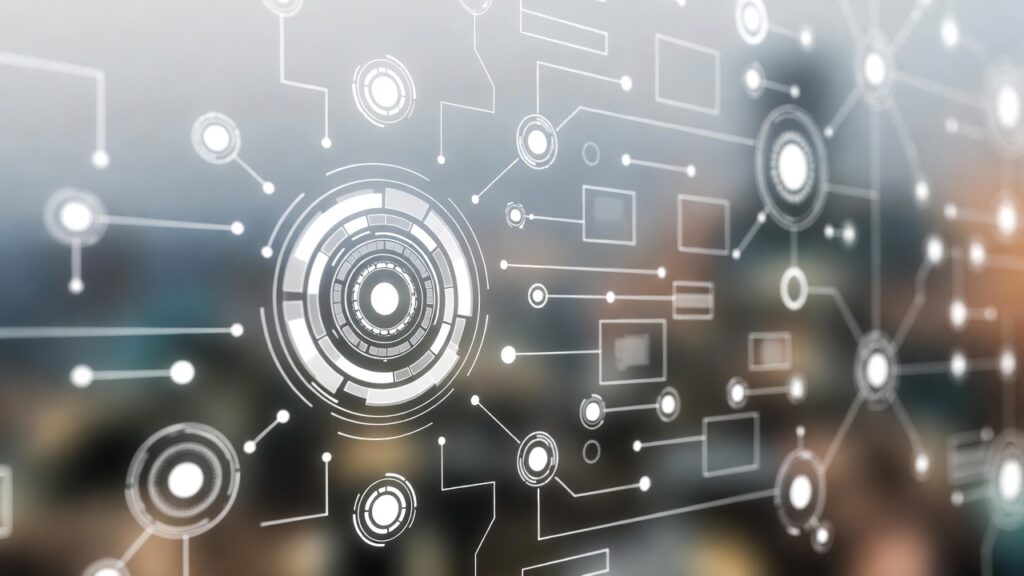
AIエージェントのさらなる進化
2026年以降、AIエージェントは「複数のエージェントが協力して仕事をする」段階に進みます。
たとえば、「営業エージェント」が顧客に提案し、「在庫管理エージェント」が商品を確保し、「経理エージェント」が請求書を発行する…という具合に、複数のAIが連携して業務全体を自動化する世界が現実になりつつあります。
Gartnerの予測によると、2030年までにAIネイティブ開発プラットフォームの普及により、組織の80%が大規模なソフトウェアエンジニアリングチームを再編すると見込まれています。
量子コンピューティングとの融合
2026年末までに「量子優位性」(量子コンピュータが従来のコンピュータを超える精度・効率を達成すること)が実現する可能性が高いと予測されています。
これが実現すると、従来は不可能だった規模のシミュレーションや最適化計算が可能になり、新素材開発、金融取引の最適化、創薬研究などが大きく加速すると期待されています。
人間とAIの新しい関係
「AIに仕事を奪われる」という不安がある一方で、「AIと協働することで、より創造的な仕事に集中できる」という前向きな見方も広がっています。
実際、定型業務がAIに移行することで、人間は「戦略立案」「創造的な企画」「人間関係の構築」といった、AIには難しい仕事に専念できるようになります。
重要なのは、AIを「競争相手」ではなく「協力者」として捉え、AIと共に成果を出せる人材になることです。
おわりに:まず一歩を踏み出そう
「業務分析」「データ利活用」という言葉は難しく聞こえますが、本質はシンプルです。
- 業務分析:今の仕事のやり方を見直して、もっと良くできないか考える
- データ利活用:持っている情報を活かして、より良い判断をする
どちらも、特別な技術や莫大な投資がなくても始められます。
大切なのは、「完璧を目指さない」ことです。まずは身近なデータを使って、小さな分析から始めてみてください。Excelで売上の推移を可視化するだけでも、新しい気づきが得られるかもしれません。



2026年は、AIとデータ活用が「一部の先進企業だけのもの」から「すべての企業に必要なもの」へと変わる転換点です。この波に乗り遅れず、自社なりのデータ活用を始めてみてはいかがでしょうか。










コメント