真正性とは
真正性(Authenticity)とは、情報や通信の発信元が正当であり、改ざんやなりすましが行われていないことを保証する性質を指します。
情報セキュリティの三要素「CIA(機密性・完全性・可用性)」に加え、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)では「真正性」「責任追跡性」「否認防止」なども重要な要素とされています。
簡単に言えば、真正性は「その人が本当に本人か?」「その情報が本当に正しい発信元から来たのか?」を確認する仕組みです。
 ITTI
ITTI具体的なイメージとしては、顔認証や指紋認証といったバイオメトリクス(生体認証)があります。パスワードは盗まれれば簡単に突破されますが、生体認証は身体的特徴を利用するため、なりすましが難しく安全性が高いのです。
さらに、二段階認証(2FA)を組み合わせることで、仮にパスワードが漏洩しても不正利用を防ぐことができます。
バイオメトリクス認証とは、人間の身体的・行動的特徴を利用して本人確認を行う「生体認証」技術のことです。 要するに、自分の体を使って解錠する。



要するに、真正性とは「本人であることを確かめる仕組み」であり、パスワードだけに頼らず、生体認証や二段階認証を組み合わせることで、より強固に守ることができるのです。
真正性が重要な理由


• 企業の場合:取引先からのメールが偽装されていたら、誤って送金し大きな損害につながる
• 個人の場合:ネットショッピングで偽サイトにアクセスすれば、クレジットカード情報を盗まれるリスクがある
• 社会全体:選挙や行政手続きで「なりすまし」が起きれば、制度そのものへの信頼が崩壊する
• クラウド利用の場合:正規のサービスを装った偽アプリや偽APIにアクセスすると、データ流出やマルウェア感染につながる



真正性が欠ければ、人も組織も容易に騙されます。最悪の場合、標的となり社会的信頼を失うリスクすらあります。
だからこそ、真正性はセキュリティの最低条件であり、これを欠いた仕組みは他をどれだけ強化しても脆弱なのです。
真正性の具体例


• 日常生活:LINEやメールで「本人確認コード」が送られてくる → 本人であることを確認する仕組み
• ビジネス:電子契約サービスでデジタル署名を利用 → 契約書が正しい相手から送られたことを保証
• ITシステム:WebサイトのSSL証明書 → 「このサイトは正規の運営者によるもの」とブラウザが確認
• SNS:公式アカウントの認証バッジ → なりすましではなく本物の発信者であることを示す
真正性は「宅配便の受け取りサイン」と同じ。サインがあることで「確かに本人が受け取った」と証明できるのです。



基本的なことですが、知らない送信元からのメールは開かないようにしましょう。迷惑メールフォルダに振り分けられたものは触れずに削除するのが安全です。たとえ知っている相手からのメールでも、不自然な内容やリンクが含まれていれば注意が必要です。
真正性を守るには、技術的な仕組み(認証・署名・証明書)と、日常の習慣(怪しいものを避ける意識)の両方が欠かせません。
真正性を守る方法


認証技術の活用
◦ パスワード認証:最も基本的な方法
◦ 二要素認証(2FA):パスワード+SMSコードやアプリ認証
◦ 生体認証:指紋・顔認証など
デジタル証明書と電子署名
◦ SSL/TLS証明書:Webサイトの正当性を保証
◦ 電子署名:文書やデータが正しい発信元から来たことを証明
◦ 公開鍵基盤(PKI):証明書の発行・失効を管理する仕組み
アクセス制御
◦ ユーザーごとに権限を設定し、正当な利用者だけがアクセスできるようにする
◦ 最小権限の原則(必要最小限の権限だけを付与)
ログ管理と監査
◦ 誰がいつアクセスしたかを記録し、不正利用を検知できるようにする
◦ 定期的な監査で「なりすまし」や「不正アクセス」を早期発見
ユーザー教育
◦ フィッシングメールの見分け方を学ぶ
◦ 正規サイトのURLや証明書を確認する習慣をつける



教育は真正性を支える本質です。
どれだけ高度な技術を導入しても、利用者がだまされてしまえば意味がありません。
だからこそ、フィッシングの見分け方や正規サイトの確認方法といった教育を徹底し、学んだことを日常の行動に落とし込むことが、真正性を守る最後の砦となるのです。
真正性を脅かす脅威


• フィッシング詐欺:偽メールや偽サイトで本人になりすます
• 中間者攻撃(MITM):通信の途中でデータを盗聴・改ざん
• 偽造証明書:正規のように見せかけた証明書でユーザーを騙す
• マルウェア感染:正規アプリを装った偽アプリで情報を盗む
• ソーシャルエンジニアリング:人間心理を利用して本人確認を突破する



これらの脅威を見ると教育の重要性がよく分かります。ただし、中間者攻撃のように教育だけでは防げないものもあります。
その場合はVPNやTLSといった暗号化通信を利用し、「安全な通信以外は使わない」というルールを教育に組み込むことが有効です。
AIひろゆきの会話
ここからは対話形式で理解を深めてみましょう



っていう真正性についての説明でした。どうだったでしたか?



いや、真正性が大事って言いますけど、
結局「二段階認証入れましょう」とか「教育が大事です」って、
どこの会社でも言ってる当たり前の話なんですよね。
でも実際には、教育を受けても人はクリックしちゃうし、二段階認証も「面倒だからオフにする」って人が普通にいるんですよ。



だから優秀な組織って、教育とか仕組みを“やってますアピール”で終わらせないで、
「人は必ずミスをする」前提で設計するんですよね。例えば、フィッシングメールを自動で隔離するとか、証明書の更新を自動化するとか、“人に頼らなくても真正性が担保される仕組み”を作る。
結局それが、本当に優秀な会社がやってることなんですよ。



じゃあ、委託と契約すればいいんですか?



いや、委託と契約すれば安心って言いますけど、
実際には「契約書に書いてあるから大丈夫」って思考停止してる組織が多いんですよね。
委託先に任せても、その委託先がちゃんと運用してなかったら意味ないし、契約違反が起きても、裁判や調停で解決するまでに時間もコストもかかるんですよ。



結局、真正性って「紙の契約」じゃなくて、日々の運用で証明されるものなんですよね。
だから優秀な会社は、委託するにしても「監査ログを共有させる」とか、「定期的に検証テストをやる」とか、契約の外側で実効性を担保してるんですよ。契約は“看板”にはなるけど、中身が伴ってなければ、ただの飾りなんですよね。



じゃあ、どうすればいい?



完璧なんてないんで、“一番マシな方法”を選ぶしかないんですよ。用途ごとに利便性とリスクを見て、ベストじゃなくベターを選ぶ。それが現実的なんですよね。
まとめ


真正性は、情報セキュリティにおいて「その情報や相手が本物であること」を保証する最低条件です。
今日からできることは、まず 二要素認証を有効化すること、そして 怪しいリンクを避けること。この小さな習慣を怠れば、どれだけ他を強化しても信頼は守れません。
真正性を軽視する組織に待っているのは、信頼を失う未来だけです。
この記事が参考になったと感じた方は、ぜひ周りの方にも共有していただけると嬉しいです。
また、ご意見やご感想があればコメントで教えてください。今後の記事改善に役立てていきます。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


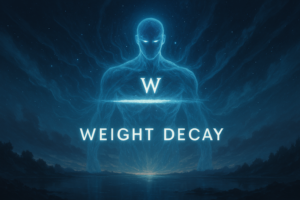
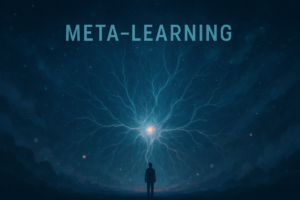


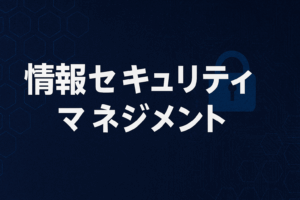
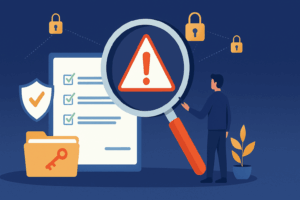
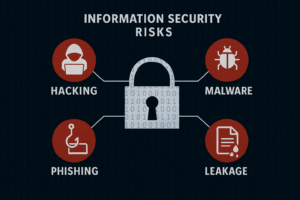

コメント